はじめに

建物の地震対策として代表的な技術には、「耐震」「制震(制振)」「免震」の3つがあります。これらの構造は、それぞれ「揺れに耐える」「揺れを吸収する」「揺れを遮断する」という異なるアプローチで、大切な人命や建物を守っています。
住宅やマンションの購入、または建築を検討する際、これらの仕組みや特徴をしっかりと理解することは、最適な選択をするために欠かせません。この記事では、三つの構造について、その仕組みの違い、特徴、そして長所・短所を、初心者の方にも分かりやすいように総まとめします。
本文
1. 建築物の地震対策の分類と目的
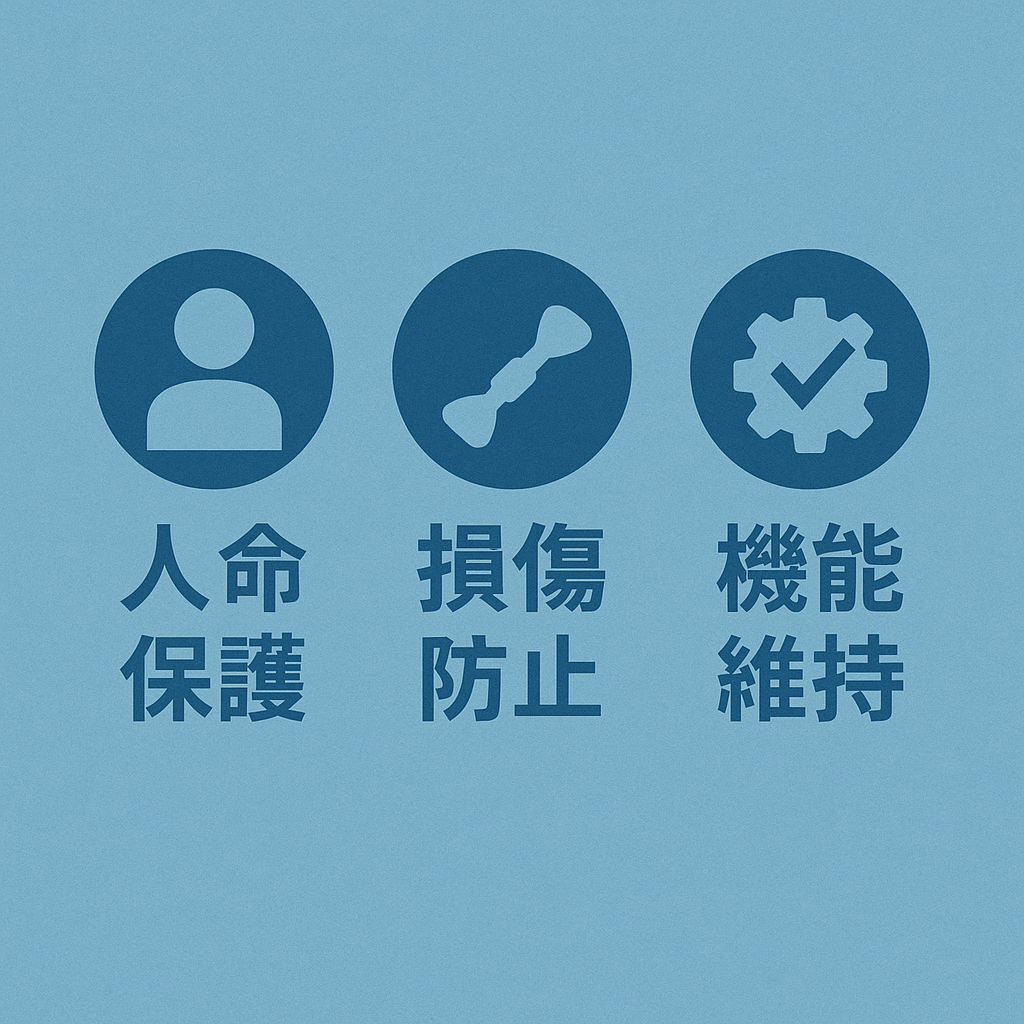
建物の構造性能は、地震に対して以下の3つの分類で評価されます。
- 人命保護:建物の倒壊や崩壊を防ぎ、建物周辺に危害を加えない最低限の性能です。
- 損傷防止:地震による建物の財産価値の喪失を防いだり、修復を容易にして価値を取り戻したりする性能です。文化的な価値を持つ建物の保護も含まれます。
- 機能維持:地震が発生した後も、建物が期待される機能を発揮し続ける性能であり、建物内の収容物の保護も含まれます。
従来からこれらの性能を守るために「耐震設計」が行われてきましたが、近年では、より高度な性能(損傷防止や機能維持)を満たすことを目的に「振動制御の設計」が積極的に行われています。この振動制御こそが「制震」と「免震」であり、いずれも耐震設計を基本として機能が付加されて設計されます。
2. 耐震構造:揺れに耐える仕組みと特徴

仕組みと概要
耐震は、建物自体を頑丈に強くして、地震の揺れ(地震力)に耐えようとする設計方法です。
柱や壁を頑丈にしたり、壁に筋かいを入れたり、部材の接合部を金具で補強したりすることで、建物が変形しないように抑え、倒壊・崩壊を防ぎます。地震の力は主に重量のある床や屋根にかかるため、柱や梁なども含めて建物全体をバランスよく補強する必要があります。
耐震構造は、最も一般的な構造であり、一戸建て住宅やマンション、オフィスビルなど、幅広い建物で採用されています。
長所(メリット)
- 建設コストが安い:免震や制震と比較して、建設コストを抑えられます。そもそも建築基準法による耐震基準(最低限の基準)を満たす必要があるため、建物を建てる際に耐震の建物はできあがります。
- 工期が短い:特殊な工事が少ないため、工期をそれほど長くかけずに済みます。
- 自由に設計しやすい:設計上の大きな制約が少ないことがメリットです。
短所(デメリット)
- 建物が損傷しやすい:人命保護の使命はおおむね果たすことが可能ですが、激しい振動が生じた際は、建物自体に損傷が生じ、機能維持が難しくなる場合があります。
- 上の階ほど揺れが大きくなる:地盤の揺れが直接的に建物に伝わるため、特に高層のマンションなどでは上の階ほど揺れが大きくなってしまいます。
- 繰り返しの揺れに弱い:何度も地震力(揺れ)を受けることで部材の損傷が大きくなり、最悪の場合、倒壊してしまう可能性もあります。
- 二次被害が起こりやすい:建物の損傷がない場合でも、大きな揺れによって家具の転倒や物の落下といった二次被害が起こりやすいです。
3. 制震構造:揺れを吸収する仕組みと特徴

仕組みと概要
制震(制振)とは、建物に入った地震の揺れを特殊な装置で吸収させ、建物の揺れを収まりやすくする方法です。
具体的には、建物内に制震ダンパーやマスダンパー(TMDやAMD)などの制震装置を設けます。これらの装置は振動に対し抵抗力を作用させて減衰させることで揺れを抑えます。制震装置は揺れを熱エネルギーに転換して空気中に放出し、揺れを小さくすることで建物を倒壊しにくくします。
制震は、建物の揺れの増幅を防ぎ、早く揺れを収めるため、損傷防止や機能維持の性能も併せ持ちます。高層ビルやタワーマンションのように上階の揺れが増幅する傾向がある建物で特に採用されます。
長所(メリット)
- コストと強度のバランスが良い:免震と比べると建設コストが安く、耐震よりも地震による被害を抑えることができます。
- 繰り返しの揺れに強い:余震など、繰り返しの揺れにも強いため、建物の被害を受けにくくできます。
- 台風などの揺れにも対応:地震動だけでなく、台風などの強風による揺れにも対応できるメリットがあります。
- メンテナンスが比較的容易:地震後のダンパーの取り替えは不要な場合が多く、鋼材ダンパーなどは定期的なメンテナンスも不要とされています(ただし、オイルダンパーやゴムダンパーは定期的な点検が必要です)。
短所(デメリット)
- 地盤の影響を受けやすい:免震とは異なり、地盤の揺れが建物に直接伝わります。そのため、地盤が軟弱な土地に建てられた場合、十分な制震効果が得られない可能性があります。
- 1階は揺れが伝わる:地表面に近い1階は、地表面と同じくらい揺れが伝わります。
4. 免震構造:揺れを遮断する仕組みと特徴

仕組みと概要
免震は、地震時の揺れを遮断(建物に揺れを伝わりにくく)する設計です。
建物と地盤を切り離した構造であり、建物と基礎の間に、揺れを吸収するダンパーや、建物を支える積層ゴム(アイソレータ)などの特殊な免震装置が設けられます。この装置が地震の力を受け流すことで、上部建物に加わる揺れを大幅に低減させます。
免震の大きな特徴は、耐震や制震と比較して、大きな地震が発生しても建物は揺れにくいことです。これにより、人命保護だけでなく、損傷防止、機能維持について最も高い性能を実現できます。
長所(メリット)
- 揺れが最も小さい:地震に対する最も優れた構造といえます。建物が大きく揺れることはありません。
- 二次被害を防ぐ:建物の揺れが小さいため、家具の転倒や移動、物の落下なども起こりにくくなります。
- 建物内部の損傷防止:通常は目に見えない壁の内部や部材の接合部などの損傷も起こりにくく、大切な資産をしっかりと守れます。
短所(デメリット)
- 建設コストが高い:耐震や制震に比べ、コストが最も高くなります。また、施工会社も限られています。
- ランニングコストがかかる:定期的な点検と、メンテナンスや交換が必要となり、ランニングコストもかかります。
- 縦揺れや強風に弱い:免震は横揺れの地震には大きな効果を発揮しますが、縦揺れの地震や台風などの強風には効果を発揮しにくいとされています。
- 設計上の制約:免震装置を設置するスペースが必要になるほか、設計上の制約が生じることがあります(例えば、地下室が設けられないなど)。
- 歴史が浅い:免震の工法の歴史はまだ浅く、免震装置に使用されているゴムの耐用年数(60〜80年)が完全に実証されているわけではありません。
まとめ
「耐震」「制震」「免震」は、それぞれ異なる地震へのアプローチを持ち、建築の目的や予算に応じて最適な選択が変わってきます。
特に、建物の保護や機能維持を重視するなら、制震や免震を検討すべきですが、コストを最優先するなら耐震構造が有利です。
| 構造 | 仕組み | 揺れの低減効果 | コスト | 主な特徴と注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 耐震 | 建物自体を強くして耐える | 低(倒壊防止が主目的) | 最も安い | 人命保護は可能だが損傷しやすい。上階の揺れが大きく、二次被害が起こりやすい。 |
| 制震 | 装置で揺れを吸収する | 中~高 | 免震より安い | 余震や台風にも強く、損傷防止に優れる。ただし、地盤の影響を受けやすく、1階は揺れやすい。 |
| 免震 | 装置で揺れを遮断する | 最も高い | 最も高い | 建物と収容物の保護性能が最も高い。縦揺れや強風には効果が限定的。ランニングコストがかかる。 |
どの構造で建てられた住宅を選ぶとしても、完全に地震による被害をなくせるわけではありません。家具の転倒などを防ぐため、自分でできる地震対策も合わせて講じることが大切です。


コメント