はじめに
マイホームの品質や性能は、地震への強さや日々の光熱費、将来のメンテナンス費用にも直結する重要な要素です。しかし、住宅の良し悪しを自己判断するのは非常に難しいものです。
そこで役立つのが、住宅性能評価制度です。
この記事では、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士の知見を含む提供されたソースに基づき、「住宅性能評価」の制度についてわかりやすく解説します。
住宅購入者や建築主にとって、品質が保証された住宅であることは大きな安心材料となります。この制度を理解し、より良い住宅選びに役立ててください。

本文
1. 住宅性能評価制度と評価書の種類
🔵 住宅性能評価とは?
住宅性能評価とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」に基づき、住宅の性能を客観的に評価・表示する制度です。
この制度では、国に登録した第三者機関(登録住宅性能評価機関)の専門家が、全国共通のルールに従って公正な立場で住宅の設計や建築における性能を評価します。評価の結果は等級や数値で分かりやすく表示されるため、消費者は住宅性能を比較する際の指標として利用できます。
なお、住宅性能評価は任意の制度であり、取得は必須ではありません。評価書を取得するかどうかは消費者である住宅購入者の判断となり、費用は消費者の負担になります。
🔵 評価書の種類と取得のタイミング
住宅性能評価書には、評価を行うタイミングによって主に2種類あります。
| 評価書の種類 | 評価の対象 | 申請のタイミング |
|---|---|---|
| 設計住宅性能評価書 | 建築前の設計図面、計算書など | 設計段階で申請します。着工後でも申請は可能ですが、修正の是正が困難になるリスクがあります。 |
| 建設住宅性能評価書 | 実際の建設過程と完成後の住宅 | 施工中から完成後にかけて、特定のタイミングで申請・検査を受ける必要があります。適切なタイミングを逃すと評価を受けられません。 |
重要なポイントは、建設住宅性能評価は、原則として設計住宅性能評価を受けた住宅のみ受けられるという点です。
2. 住宅性能評価の評価項目と等級の見方
新築住宅の性能評価は、以下の10分野にわたり、全体で32項目が評価されます。評価結果は等級や数値で示され、数字が大きいほど性能が高いことを意味します。
| 評価分野(10分野) | 概要と主な等級表示 | 必須か選択か |
|---|---|---|
| 1. 構造の安定 | 地震や台風、積雪に対する構造躯体の倒壊等のしにくさ、損傷の生じにくさ(耐震等級など)。 | 必須 ★ |
| 2. 火災時の安全 | 火災の早期覚知、延焼防止性能、避難安全性(耐火等級など)。 | 選択 |
| 3. 劣化の軽減 | 構造躯体等の耐久性、大規模改修を必要とするまでの期間を延ばす対策の程度(劣化対策等級)。 | 必須 ★ |
| 4. 維持管理・更新への配慮 | 給排水管、ガス管などの配管類の清掃、点検、補修を容易とする対策の程度(維持管理対策等級)。 | 必須 ★ |
| 5. 温熱環境・エネルギー消費量 | 外壁・窓等を通しての熱損失防止(断熱等性能等級)や、一次エネルギー消費量の削減対策。 | 必須 ★ |
| 6. 空気環境 | ホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策、換気対策。 | 選択 |
| 7. 光・視環境 | 居室の開口部の面積の割合(単純開口率)や、方位別の比率。 | 選択 |
| 8. 音環境 | 上下階や隣戸への音の伝わりにくさ、空気伝搬音の遮断の程度(共同住宅の場合が多い)。 | 選択 |
| 9. 高齢者等への配慮 | 住戸内や共用部分におけるバリアフリー設計や安全性の対策の程度(高齢者等配慮対策等級)。 | 選択 |
| 10. 防犯 | 外部からの侵入を防止するための対策(開口部の侵入防止対策)。 | 選択 |
特に重要なのは、以下の4分野で、これらは表示が必須な項目です。他の分野は売主などが任意に選択して表示できます。
- 構造の安定
- 劣化の軽減
- 維持管理・更新への配慮
- 温熱環境
3. 住宅性能評価を取得するメリットとデメリット
住宅性能評価書を取得することで、客観的な品質保証が得られるだけでなく、さまざまな優遇措置を受けられます。
🟦 評価書を取得する【メリット】
メリット 1:住宅の品質保証と安心感 第三者機関が評価するため、住宅の品質や性能が客観的な基準に基づいて保証されます。また、設計段階から評価を受けることで、設計ミスや施工不良を未然に防ぐ欠陥住宅の抑止力にもなります。
メリット 2:売却時の資産価値向上 住宅性能評価書を取得していると、将来的に住宅を売却する際に高い評価を受けやすくなり、資産価値の向上につながります。
メリット 3:住宅ローンや保険の優遇
- 住宅ローン金利優遇: 一部の金融機関では、評価を取得した住宅に対して金利優遇が行われます。例えば、「フラット35」では、長期優良住宅であればフラット35Sという金利引き下げメニューを利用できる場合があります。
- 地震保険料の割引: 評価書に記載されている耐震等級に応じて、地震保険料が割引されます(耐震等級3で50%引きなど、2014年7月1日以降の保険始期の場合)。
メリット 4:公的制度の利用とトラブル防止
- 贈与税の非課税枠拡大: 一定の省エネ等住宅の基準(断熱等性能等級4以上など)を満たしている場合、住宅取得等資金の贈与税非課税枠が1,000万円まで拡大します(その他の住宅は500万円まで)。
- トラブル対応(紛争処理)の申請: 設計評価と建設評価の両方を取得した住宅は、契約に関するトラブルが生じた場合、国が指定する住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)へ相談を申請できます。裁判よりも安価(1件1万円から)かつ迅速な解決が期待できます。
🟥 評価書を取得する【デメリット】
デメリット 1:費用とコスト増加の可能性 評価を受けるための手数料(評価手数料)が発生します。一般的に相場は10万円から20万円程度と言われています。また、高性能な基準を満たすために設計や材料を見直すと、その分の建築費がかさむ可能性があります。
デメリット 2:手続きの煩雑さと工期の延長 評価を受けるための書類作成や申請手続きに手間がかかります。また、評価機関の検査スケジュールに合わせる必要があり、工事の進捗が遅れる(工期の延長)可能性があります。
デメリット 3:設計・施工の制約 性能基準を満たす必要があるため、設計や材料の選択に制約が生じ、設計の自由度が低下することがあります。例えば、採光を重視して窓を大きくすると耐震性が下がるなど、相反する評価項目もあり、すべての項目で最上位の等級を目指すのは非常に難しい場合があります。
4. 住宅性能評価書を取得する流れ(新築住宅)
新築住宅で設計評価と建設評価の両方を取得する場合、以下のステップで進められます。
🟦 ステップごとの実施内容
- 事前相談 専門機関(登録住宅性能評価機関)に連絡し、申請に必要な書類や手続き、スケジュールなどを確認します。
- 設計性能評価の申請・審査 設計図面や計算書などを評価機関に提出し、基準に適合しているかの審査が行われます。問題があれば「質疑表」が送付され、対応(図面の修正等)が必要です。
- 設計住宅性能評価書の交付 審査完了後、設計内容の評価に基づき評価書が交付されます。
- 建設性能評価の申請・検査 第一回現場検査が行われる前に、建設性能評価の申請を行います。工事中にその工程ごと(基礎、躯体、完成など)に現場の検査が実施されます。
- 建設住宅性能評価書の交付 すべての現場検査と審査が完了し、検査済証の交付後に評価書が交付されます。軽微な補修でクリアできる場合は、再度検査を受けることができます。
まとめ
住宅性能評価は、「品確法」に基づき、第三者機関が住宅の性能を客観的に評価し、等級や数値で表示する任意の制度です。評価制度の利用には費用や工期増加のリスクがありますが、住宅の長期的な安心と経済的な優遇措置を考慮すると、取得を検討する価値のある重要な制度と言えます。


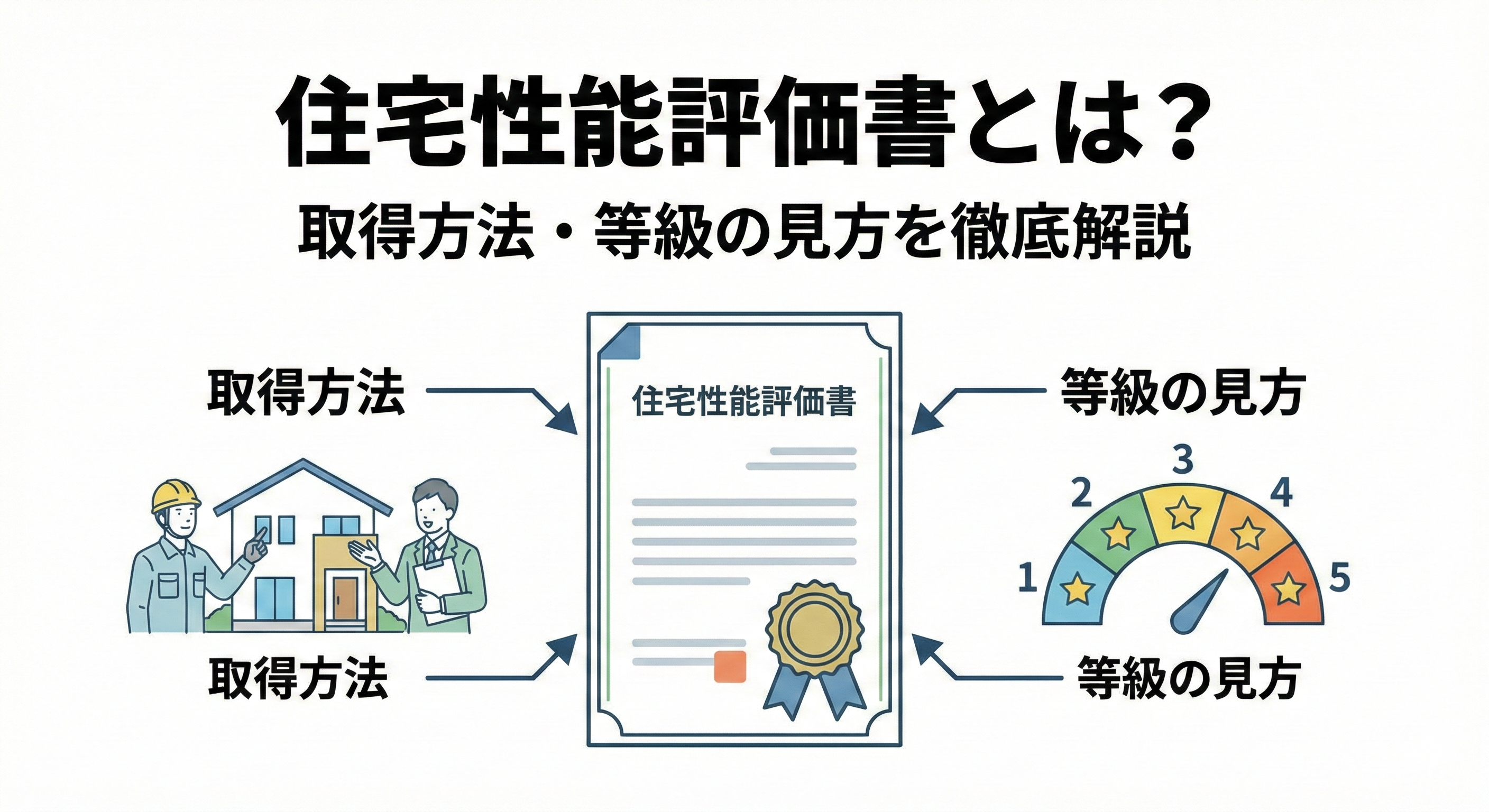
コメント