建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律です。この法律の目的は、建築物の安全性を確保することにより、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉を増進させることにあります。
もし建築物に規制がなければ、コストのみを重視した危険な建物が無秩序に建築され、倒壊などの大きな事故につながるおそれがあります。
建築基準法は、震災の発生や不祥事などをきっかけとして、これまでも不断に改正が行われてきましたが、2025年にも大きな改正が予定されています。今回の改正は、主に省エネ対策の加速、建物の安全性向上、そして木材の利用促進を背景としており、特に確認申請の手続きや構造計算の義務範囲に大きな影響を与えます。
本記事では、建築基準法の概要を解説したうえで、2025年4月1日に施行される主な改正ポイントをリストアップし、企業への影響についてわかりやすく解説します。
📘 建築基準法の基礎知識
建築基準法による規制は、適用範囲や目的に応じて「単体規定」と「集団規定」の2つに大別されます。
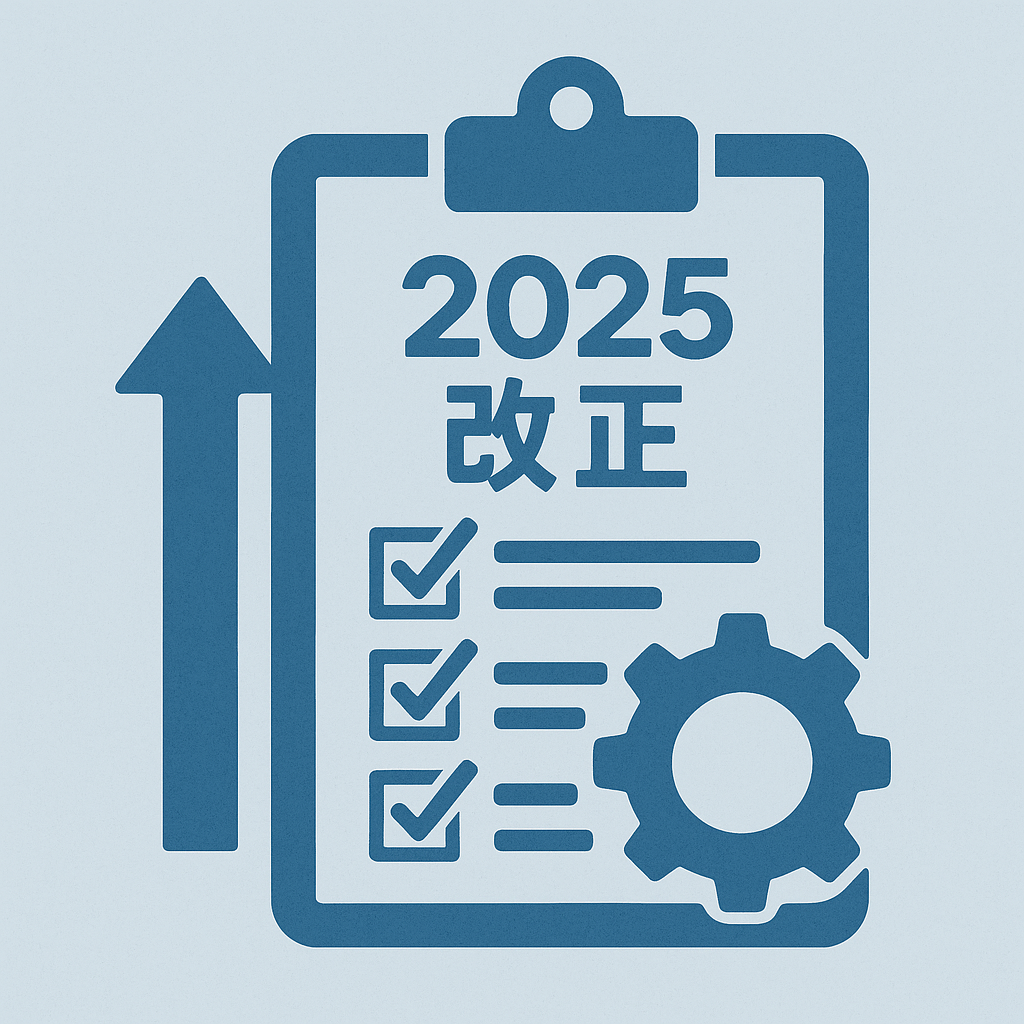
1. 単体規定(安全性・衛生に関する全国基準)
単体規定は、建築物個々の安全性や衛生の確保を目的としており、地域を問わず全国的に適用されます。
主な単体規定の内容には、以下のものが含まれます。
| 規制の種類 | 概要 | 根拠法例 |
|---|---|---|
| 敷地に関する規制 | 敷地の高さや地盤強度、雨水・汚水処理施設、がけ崩れ防止措置など。 | 法19条 |
| 構造耐力に関する規制 | 地震や台風に備えた構造耐力基準への適合義務。一定規模以上の大規模建築物にはより厳しい基準が適用。 | 法20条、21条 |
| 防火・避難に関する規制 | 屋根や外壁の防火性能、防火壁の設置義務、避難経路の確保など。 | 法22条、35条など |
| 一般構造・設備に関する規制 | 居室の採光・換気、アスベスト飛散防止、便所の構造、建築材料の品質など。 | 法28条、31条など |
2. 集団規定(都市計画に関する地域基準)
集団規定は、計画的な都市運営を目的としており、都市計画区域および準都市計画区域に存在する建築物についてのみ適用されます。
主な集団規定の内容は以下のとおりです。
| 規制の種類 | 目的と内容 |
|---|---|
| 接道規制 | 災害時の避難経路や緊急車両の接近経路を確保するため、敷地が原則幅員4m以上の道路に2m以上接することを義務付ける。 |
| 用途規制 | 無秩序な都市化を防ぐため、地域ごとに13種類の用途地域を設定し、建築できる建物の種類や規模を制限する。 |
| 形態規制 | 防災や住環境保全のため、容積率(土地に対する延べ床面積の割合)や建ぺい率(土地に対する建築面積の割合)、高さ制限などを設ける。 |
3. 建築確認と検査による遵守のチェック
周囲に与える影響が大きいと考えられる建築物を建築、大規模の修繕、または大規模の模様替をする際は、工事に着手する前に、計画が基準に適合しているか否かをチェックする「建築確認」を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
また、工事完了時には、確認を受けた内容と合致しているかを確認する「完了検査」を受ける必要があります。
💡 【2025年4月1日施行】改正の主なポイントリストアップ
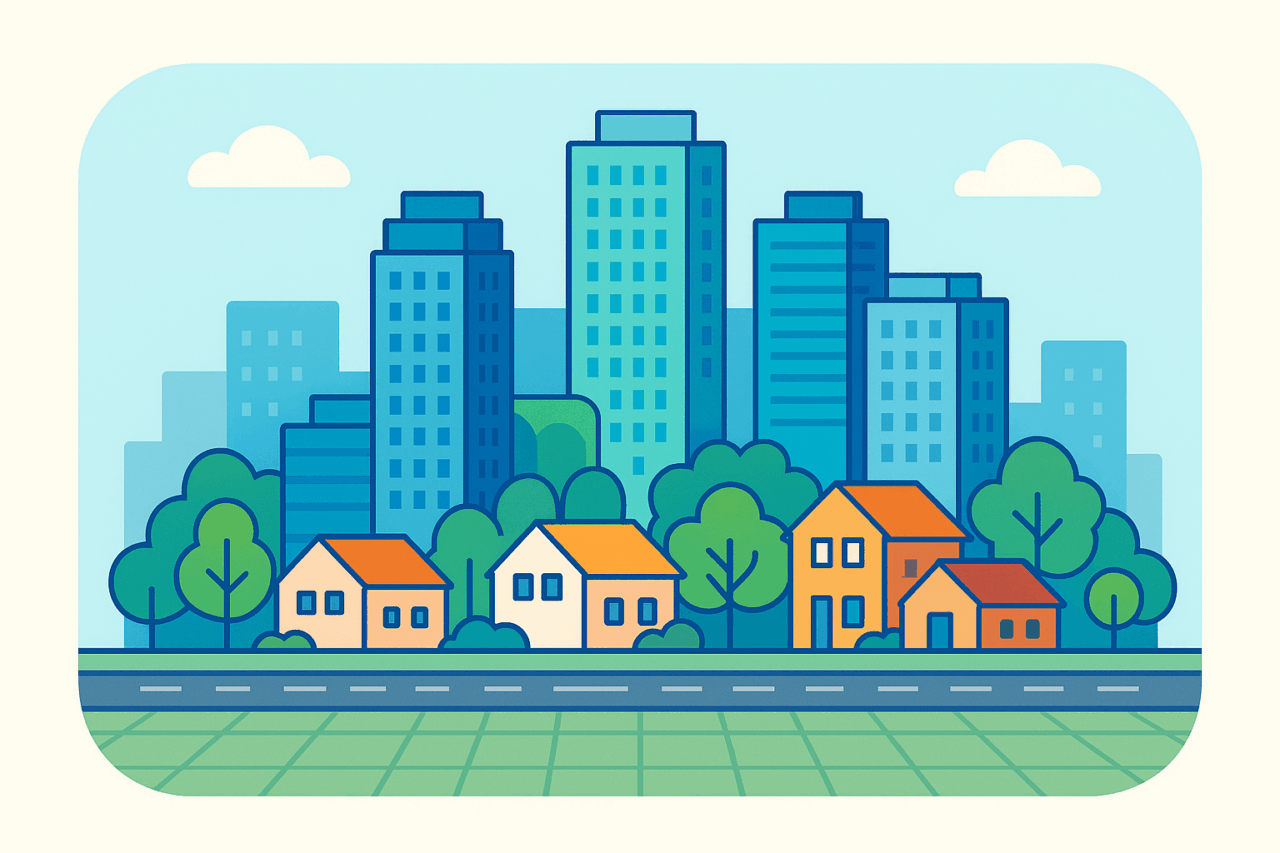
今回の建築基準法改正の多くは、2025年(令和7年)4月1日以降に工事着手(着工)するものから適用されます。
特に重要な改正ポイントは、「建築確認・検査対象の見直し(4号特例の縮小)」、「省エネ基準の適合義務化」、そして「小規模木造建築物の構造関係規定の見直し」の3点です。
1. 建築確認・検査対象の見直し(4号特例の縮小)
これまで、特定の小規模な木造建築物は「4号特例」として、確認申請における審査の一部(主に構造関係規定や集団規定の一部)が免除されていました。
この「4号特例」の対象範囲が大幅に縮小されます。
| 項目 | 改正内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建築確認対象の変更 | 木造建築物の建築確認・検査対象の規模が見直される。 | 従来の木造建築物とその他の建築物で異なっていた規模要件が、非木造と同様の規模となる。 |
| 「4号特例」の縮小 | 従来の4号建築物は、改正後「新2号建築物」「新3号建築物」に分類される。 | 木造2階建て住宅は延べ面積に関わらず「新2号建築物」となり、特例から外れる。確認申請で構造審査および省エネ適判が必要となる。 |
| 申請対象の拡大 | 都市計画区域外においても、改正前は申請が免除されていた小規模建築物の一部が、新たに申請対象となる。 | 「新3号建築物」(平家建てかつ延べ面積200㎡以下など)はこれまで通り審査が免除される。 |
| 提出図書の合理化 | 新2号建築物のうち、仕様規定のみで適合するものは、基礎伏図や軸組図などの一部図面の提出が省略可能。 | 仕様表などに必要事項を記載することで代替。 |
2. 全ての建築物への省エネ基準適合義務化
2025年4月1日以降、原則として全ての建築物に対し、省エネ基準への適合が義務化されます。基準を満たさなければ、建築確認申請で確認済証が交付されません。
| 項目 | 改正内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 義務化の範囲 | 原則全ての新築・増改築に適用。 | 床面積10㎡以下のもの、歴史的建造物などは免除される。 |
| 満たすべき基準 | 建築物の用途により異なる。 | 住宅: 外皮性能基準(外壁・窓などの熱損失量)および一次エネルギー消費量基準。非住宅: 一次エネルギー消費量基準。 |
| 適合性の確認 | 建築確認申請時に確認。 | 省エネ適判(適合性判定)を受けるか、【住宅のみ】 国土交通省が定める仕様基準を満たす。 |
| 大規模非住宅の基準強化 | 床面積2000㎡以上の非住宅建築物について、省エネ基準が引き上げられる。 | 工場等は現行のBEI 1.0から0.75へ、事務所等は1.0から0.80へ基準が強化。 |
3. 小規模木造建築物の構造関係規定の見直し
建物の安全性をさらに向上させるため、特に省エネ化に伴い重量化する木造建築物に対応できるよう、構造安全性の検証法が合理化・強化されます。
| 項目 | 改正内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 構造計算義務の拡大 | 2階建て以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模が引き下げ。 | 延べ面積が500㎡超から300㎡超に変更される。 |
| 簡易構造計算範囲の拡大 | 簡易な構造計算が認められる範囲が拡大。 | 従来の「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から、「階数3以下かつ高さ16m」へ拡大。 |
| 壁量基準の変更 | 必要壁量の算定方法から、「重い屋根」「軽い屋根」の指標が廃止。 | 建築物の荷重の実態に応じた計算式(Lw= Ai⋅C0⋅∑wi/0.0196⋅Afi)により算定する。 |
| 筋かいの対象拡大 | K型筋かいや多段筋かいなども、大臣認定の取得により使用可能となる。 | 木材や鉄筋と同等以上の強度を有する材料の使用が新たに認められる。 |
| 基礎の基準の見直し | 地盤の種別に関わらず、無筋コンクリート基礎が廃止され、鉄筋コンクリートの基礎を用いることが義務化される。 | 平成12年告示第1347号が改正される。 |
🏢 企業が受ける主な影響と注意点
2025年4月1日施行の改正建築基準法は、特に建設業界だけでなく、社屋の建設やリフォームを予定している一般の企業にも大きな影響を与える可能性があります。

1. リフォームや建築時のコスト増加の可能性
改正により、従来は構造計算や建築確認が不要であった建物でも、これらが必要となるケースが増えました。
従来は構造計算や建築確認が不要であった建物であっても、改正後はこれらが必要となるケースが増えたためです。
- 構造計算や申請費用の発生: 構造計算が必要となれば、設計者の業務が増加し、コストが増大します。
- 省エネ基準対応コスト: 建築基準法と同時に改正された省エネ法によって、より高い断熱性能などが求められるため、この点からもコストが増大する可能性があります。
2. リフォームや建築の工期長期化の可能性
構造計算や建築確認が必要となった場合、その計算や申請に時間を要するため、従来よりも工期が長期化する可能性があります。
また、改正法は「着工日」を基準として適用されます。2025年4月1日よりも前に確認済証を受けていても、着工が4月以降になる場合は、完了検査時に省エネ基準の適合確認が必要となるため、計画の遅延には十分な注意が必要です。
建築基準法は、建築物の安全性や衛生を確保し、公共の福祉を増進するための根幹となる法律です。
2025年4月1日に施行される今回の改正は、日本の建築物全体において省エネ性能の底上げと構造安全性の強化を目的としています。
特に、「4号特例の縮小」により、木造2階建て住宅を含む多くの小規模建築物が新たに構造審査や省エネ適合性判定の対象となり、確認申請の手続きが大きく変わります。
建築やリフォームを計画している企業は、コスト増大や工期長期化のリスクを念頭に置き、設計者や施工者と密に連携し、改正内容を十分に理解しておくことが求められます。
(本記事は2025年4月1日施行の法改正に関する情報に基づいて作成されています。記事中の法令日時は執筆時点のものです。最新の情報については、必ず関係機関にご確認ください。)

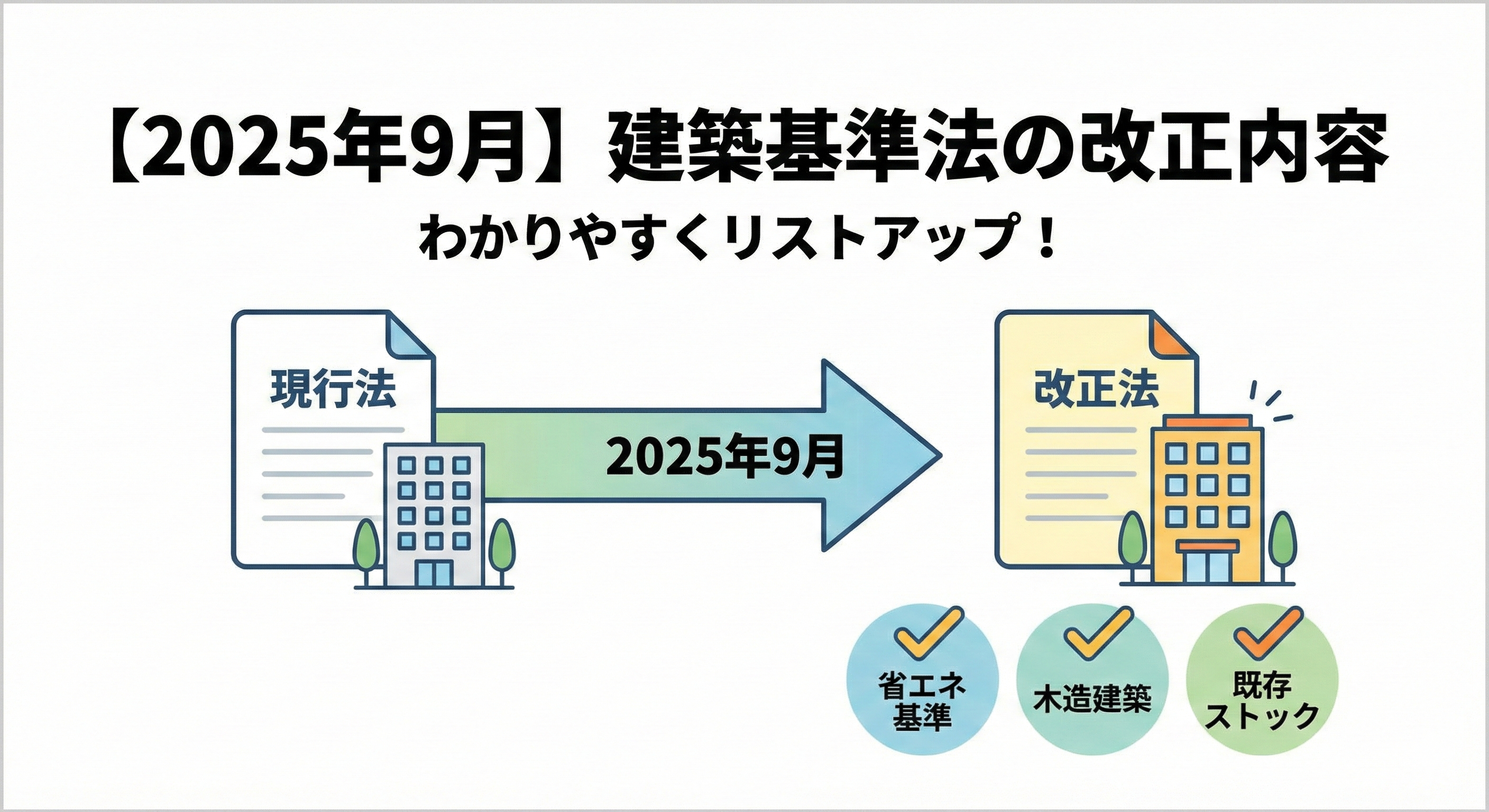
コメント